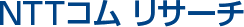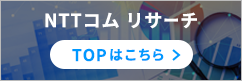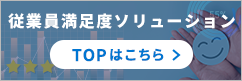gooリサーチ と japan.internet.com による共同企画調査
東日本大震災とそれに続く福島第一原子力発電所の事故で、「在宅勤務制度」を見直す風潮が生まれたようだ。
震災当初は、外資系企業などが社員の放射線被ばくを避けるため、緊急避難的に在宅勤務を社員に奨励したが、最近では、原発事故により電力供給が大幅に減少することから、より長期的な「在宅勤務制度」を検討している企業も多いだろう。
そこで、インターネットコムとgooリサーチでは、「在宅勤務制度」に関する調査を行ってみた。
調査対象は、全国(一部被災地エリアを除く)10代~60代以上のインターネットユーザー1,072人。男女比は男性52.9%、女性47.1%、年齢別は10代17.0%、20代18.1%、30代21.3%、40代16.0%、50代15.8%、60代以上11.8%。
全体1,072人のうち、官庁や地方自治体、民間企業に勤務していると回答した47.4%(508人)に対し、勤務先での「在宅勤務制度」の有無、「在宅勤務制度」の問題点と有利な点を聞いてみた。
その結果、508人のうち、勤務先に「在宅勤務制度」があると回答したのは、わずか8.3%(42人)だった。これに、「現在はないが、近いうちにできる予定」0.8%(4人)、「現在検討中」4.7%(24人)を加えても、13.8%(70人)にしかならない。
調査対象が違うので比較するのは難しいが、2007年11月に行った調査では、13.0%が、勤務先に「在宅勤務制度」がある、と回答している。
約3年半経過しても、あまり普及の進んでいない「在宅勤務制度」であるが、ユーザー自身は、「在宅勤務制度」の問題点として「仕事のコミュニケーションがとりにくい」(314人)、「自宅に必要な機器がそろっていない」(258人)、「勤務時間がルーズになる」(226人)などをあげている。
それでは、「在宅勤務制度」の有利な点は何だろうか。
ユーザーは、「通勤時間がない」(407人)、「勤務スケジュールを自分で決められる」(360人)、「服装をきにしなくてすむ」(293人)などをあげている。
勤務時間の自己管理能力はユーザー自身が身につけていくしかないが、それ以外の、仕事に必要なコミュニケーションツールや機材は、勤務先が用意すべきものだろう。
今回の震災を機に、それらをどの程度、官庁や地方自治体、企業が職員や社員の自宅に導入するか、今後注目していきたいところだ。
<調査概要>
- 実施期間: 2011/05/23~2011/05/24
- 有効回答数: 1,072
NTTコム リサーチは、平成24年10月1日にエヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社からNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社へ事業譲渡され、平成25年12月9日にgooリサーチより名称変更いたしました。gooリサーチの調査結果(共同調査含む)等についてはこちらまでお問合せください。