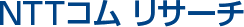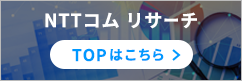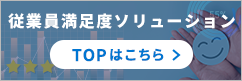2010年7月22日
NTTレゾナント株式会社
ワーキングマザー1000人調査
第2回 育児と仕事に関する調査
~今後欲しい企業の育児サポート制度は、「育児サービス利用料の補助」「事務所内保育所」~
インターネットアンケート・サービスを提供する「gooリサーチ」は、「gooリサーチ」の登録モニターの中からワーキングマザー(6歳以下の子どもを持つ既婚就業女性)を対象に「育児と仕事に関する調査」を実施しました。有効回答者数は1,000名でした。
なお、前回調査は、2007年11月19日にgooリサーチと株式会社オールアバウトの共同調査として、「育児と仕事に関する調査」~企業の育児サポート、制度が充実しているのは大きい企業 満足度が高いのは10人未満の小さい企業 ~として発表しております。
総括
6歳以下の子どもを持つ既婚女性が働く理由の第一位は「食費、生活費など家計を支えるため」となり、8割を超えました。また、今後欲しい育児サポート制度として「育児サービス利用料の補助」が最も多かったことからも、厳しい家計状況が伺えました。
「イクメン(育児を楽しむ男性/育児を積極的に行う男性のこと)」ということばが登場し、以前に比べて父親の育児参加に関心が向けられるようになりましたが、父親による会社の育児サポート制度の利用は、前回調査に引き続き「特にない」が8割を超え、実態に大きな変化はみられませんでした。また、父親の育児サポートに関する「協力度」や「満足度」は、世帯年収に比例しており、高所得層ほど育児の「協力度」も、それに対する母親の「満足度」も高い傾向がみられました。
今年の6月に支給が開始した子ども手当の支給方法については、「現在のまま(年3回でよい)」が最も多く約6割となりました。一方、「分割ではなく、毎月で欲しい」という声も、世帯年収600万円未満では3割以上となりました。
調査概要
| 今回調査 | 前回調査 | ||
|---|---|---|---|
| 1. 調査対象 | 「gooリサーチ」登録モニター (6歳以下の子どもを持つ既婚の就業女性) |
||
| 2. 調査方法 | 非公開型インターネットアンケート | ||
| 3. 調査期間 | 平成22年6月24日~ 平成22年6月29日 | 平成19年10月25日~平成19年10月26日 | |
| 4. 有効回答者数 | 1,000名 | 1,068名 | |
| 5. 属 性 |
就業形態 | ・正社員44.6% ・契約社員・派遣社員9.2% ・パート・アルバイト 38.6% ・育児休暇中7.6% |
・正社員59.6% ・契約社員・派遣社員13.3% ・パート・アルバイト 19.3% ・育児休暇中7.8% |
| 企業規模 | ・10人未満 20.2% ・10人以上30人未満 15.7% ・30人以上100人未満 17.9% ・100人以上500人未満 17.0% ・500人以上1000人未満 6.2% ・1000人以上5000人未満 7.1% ・5000人以上 8.7% ・わからない 7.2% |
・10人未満 14.4% ・10人以上30人未満 13.8% ・30人以上100人未満 16.4% ・100人以上500人未満 18.1% ・500人以上1000人未満 8.0% ・1000人以上5000人未満 11.3% ・5000人以上 12.5% ・わからない 5.5% |
|
| 世帯年収 | ・400万円未満 20.8% ・400万円以上600万円未満 29.6% ・600万円以上800万円未満 26.2% ・800万円以上 23.4% |
- (設問なし) |
|
調査結果のポイント
(1) 働く理由は「食費、生活費など家計を支えるため」が8割以上
働く目的については、前回調査同様「食費、生活費など家計を支えるため」が最も多く8割を超え、世帯年収『400万円未満』では9割を超える。また、世帯年収が高い人ほど"家計の支え"以外の目的を持つ傾向があり、世帯年収『800万円以上』では「キャリアアップ、仕事のやりがい」や「自分が自由に使える収入を得るため」がいずれも半数を超える。
(2) 今後欲しい会社の制度は「育児サービス利用料の補助」「事務所内保育所」
現在ある会社の育児サポート制度としては、「短時間勤務」が最も多く、次いで「1年以上の育児休業制度」となり、大企業ほど導入が進んでいる。
また、今後欲しい会社の育児サポート制度としては、「育児サービス利用料の補助」が最も多く、次いで「事務所内保育所」となり、子どもの預け先およびその費用が負担になっていることが伺える。
(3) 1000人規模までは、小さい企業ほど満足度が高い
会社のサポート(制度や周囲の理解)に関する満足度については、「とても満足している」が前回調査より5.1ポイント高い17.2%となり、"満足派"(「とても満足している」+「ある程度満足している」)は、約6割となった。
企業規模別にみると、『10人未満』の企業では「とても満足している」が約3割と最も多く、1000人未満の企業では、企業規模が大きくなるにつれ「満足している」が減少する傾向にある。
(4) 子どもの預け先にかかる費用は前回調査よりも低価格に
子どもの預け先にかかる費用については、「3万円~5万円未満」が最も多かった。世帯年収が低いほど、子どもの預け先にかかる費用も安く、世帯年収『400万円未満』では3万円未満の割合が約8割となった。
(5) 父親の育児に関する「協力度」「満足度」は、世帯年収に比例
父親による会社の育児サポート制度の利用は、前回調査に引き続き「特にない」が8割を超え、利用状況に変化は見られなかった。
父親の育児サポートについては、"協力派"(「とても協力的」+「ある程度、協力してくれる」)は7割、"満足派"(「とても満足している」+「ある程度、満足している」)は6割となった。また、父親の育児サポートに関する「協力度」や「満足度」は、世帯年収に比例しており、高所得層ほど育児の「協力度」も、それに対する母親の「満足度」も高い傾向がみられた。
(6) 子ども手当、「分割ではなく、毎月で欲しい」が世帯年収600万円未満では3割以上
今年の6月に支給が開始した子ども手当の支給方法については、「現在のまま(年3回でよい)」が最も多く57.9%であった。一方、「分割ではなく、毎月で欲しい」も26.5%となり、世帯年収が『600万円未満』では3割以上となった。
調査結果データ
(1) 働く目的について
働く目的については、前回調査同様「食費、生活費など家計を支えるため」が最も多く、8割を超えた。次いで、「自分が自由に使える収入を得るため(42.1%)」、「(育児から離れ)自分に戻るため(33.4%)」の順となり、「キャリアアップ、仕事のやりがい」は前回よりも5.9ポイント低い33.3%となった。【図1-1】
また、世帯年収別で見ると、世帯年収が低い人ほど「食費、生活費など家計を支えるため」が多く、『400万円未満』では9割を超える。一方、世帯年収が高い人ほど"家計の支え"以外の目的を持つ傾向があり、『800万円以上』では「キャリアアップ、仕事のやりがい(52.6%)」、「自分が自由に使える収入を得るため(51.3%)」がいずれも半数を超える。【図1-2】
【図1-1】働く目的_前回調査比較
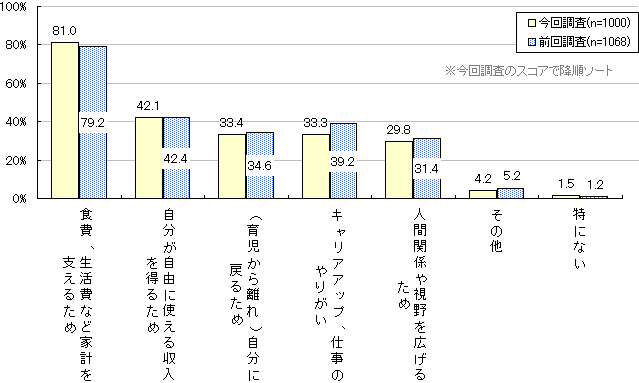
【図1-2】働く目的_世帯年収別
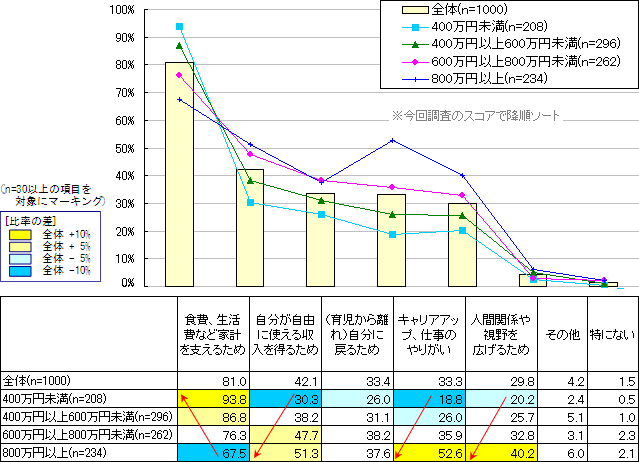
(2) 企業の育児サポート制度について
現在ある会社の制度としては、「短時間勤務(46.3%)」が最も多く、次いで「1年以上の育児休業制度(35.7%)」となる。【図2-1】
企業規模別にみると、上位2つの制度は大企業において多く導入されており、『500人以上1000人未満』『1000人以上』の企業ではどちらも6割を超える。【図2-2】
また、今後欲しい会社の制度としては、「育児サービス利用料の補助(39.0%)」が最も多く、次いで「事務所内保育所(37.8%)」となり、子どもの預け先およびその費用が負担になっていることが伺える。【図2-1】
【図2-1】育児に関する会社の制度
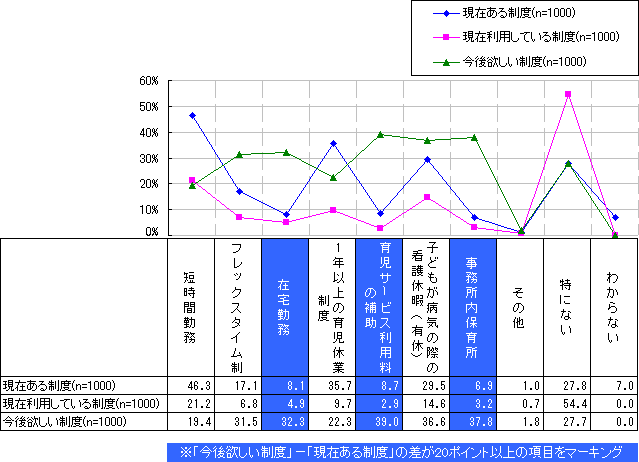
【図2-2】育児に関する会社の制度(現在ある制度)_企業規模別
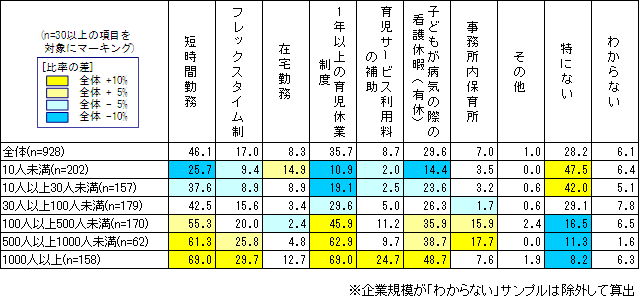
(3) 職場の周囲の理解/満足度について
職場の周囲の理解度については、「とても理解されている」が前回調査より5.0ポイント高い26.4%となり、"理解されている派"(「とても理解されている」+「ある程度理解を得られている」)は、約8割となった。【図3-1】
また、会社のサポート(制度や周囲の理解)に関する満足度については、「とても満足している」が前回調査より5.1ポイント高い17.2%となり、"満足派"(「とても満足している」+「ある程度満足している」)は、約6割となった。【図3-2】
企業規模別にみると、『10人未満』の企業では「とても満足している」が約3割と多い。企業の規模が大きくなるに従って、「とても満足している」は徐々に減り『100人以上500人未満』『500人以上1000人未満』の企業では1割にも満たない。【図3-3】
【図3-1】職場の周囲の理解度_前回調査比較
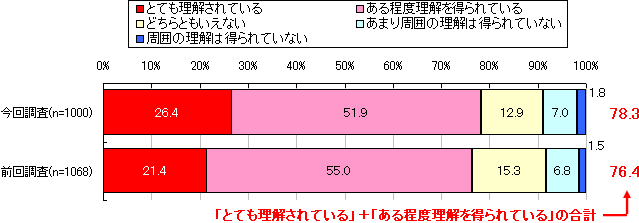
【図3-2】会社のサポート(制度や周囲の理解)に関する満足度_前回調査比較
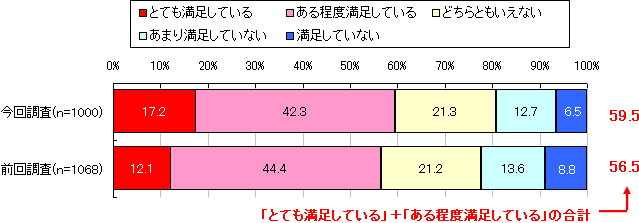
【図3-3】会社のサポート(制度や周囲の理解)に関する満足度_企業規模別
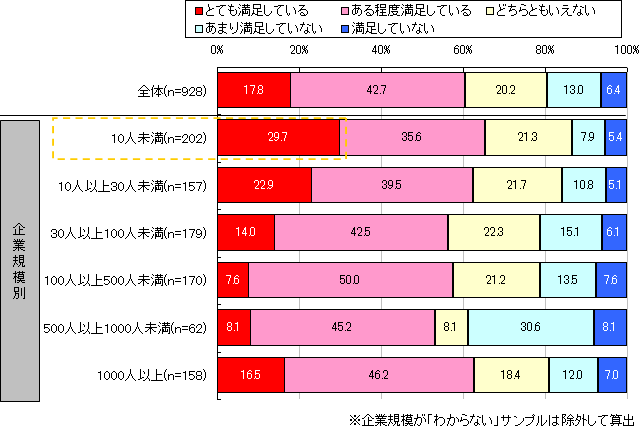
(4) 子どもの預け先にかかる費用について
子どもの預け先にかかる費用については、「3万円~5万円未満(30.5%)」が最も多く、次いで「2万円~3万円未満(26.7%)」となった。【図4-1】
また、3万円未満の割合をみると、『400万円未満(78.4%)』、『400万円以上600万円未満(65.2%)』、『600万円以上800万円未満(52.3%)』、『800万円以上満(41.1%)』と、世帯年収が低いほど増える傾向がみられた。【図4-2】
【図4-1】子どもの預け先にかかる費用_前回調査比較
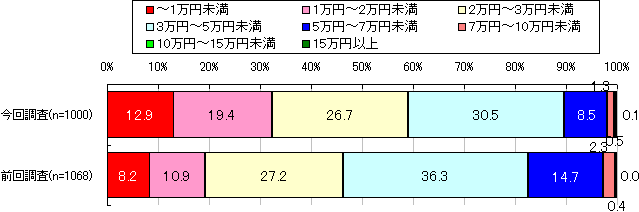
【図4-2】子どもの預け先にかかる費用_世帯年収別
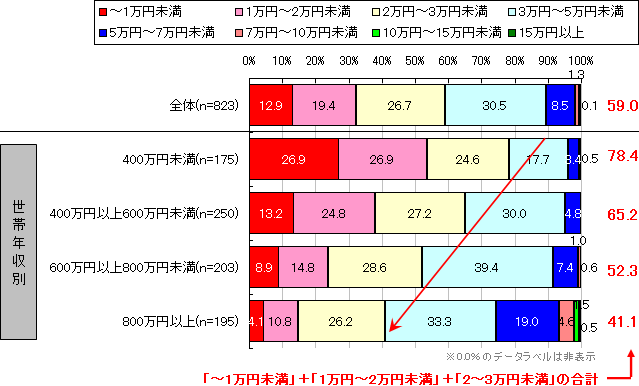
(5) 父親の育児サポートについて
父親による会社の育児サポート制度の利用について尋ねたところ、前回調査に続いて「特にない」が8割を超え、利用状況に変化はみられなかった。また、利用して欲しい制度も前回調査と同じく「こどもが病気の際の看護休暇(有休)」が51.7%と最も高く、次いで「育児サービス利用料の補助(37.3%)」となった。【図5-1】
父親の育児サポート(協力度)については、「とても協力的」が27.1%となり、"協力的"(「とても協力的」+「ある程度、協力してくれる」)は7割を超えた。世帯年収別で見ると、『800万円以上』では「とても協力的」が3割を超えており、世帯年収が高い方が、父親が"協力的"である傾向が伺える。【図5-2】
また、父親の育児サポート(満足度)については、「とても満足している」が17.8%となり、"満足派"(「とても満足している」+「ある程度、満足している」)は6割を超えた。世帯年収別で見ると、『600万円以上800万円未満』『800万円以上』では「とても満足している」が2割を超えており、高所得層の方が父親の育児サポートに対する満足度も高い傾向が伺える。【図5-3】
【図5-1】父親の会社の育児サポート制度の利用_前回調査比較
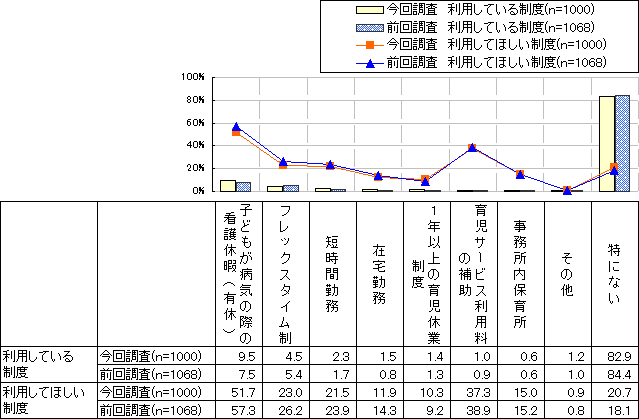
【図5-2】父親の育児サポート(協力度)_前回調査比較・世帯年収別
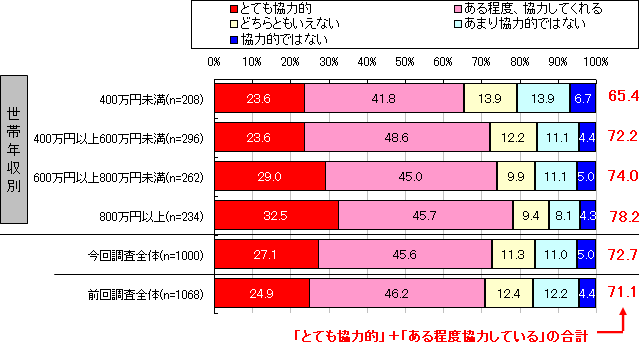
【図5-3】父親の育児サポート(満足度)_前回調査比較・世帯年収別
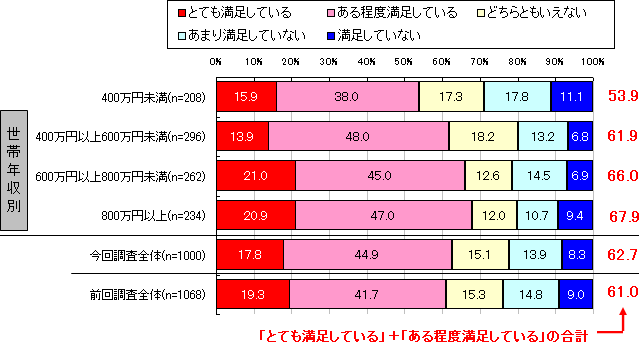
(6) 子ども手当について
今年の6月に支給が開始した子ども手当の支給方法について尋ねたところ、「現在のまま(年3回でよい)」が最も多く57.9%となった。次いで、「分割ではなく、毎月で欲しい(26.5%)」となり、世帯年収が『400万円未満』『400万円以上600万円未満』では3割以上となった。【図6-1】
【図6-1】子ども手当の支給方法について_世帯年収別
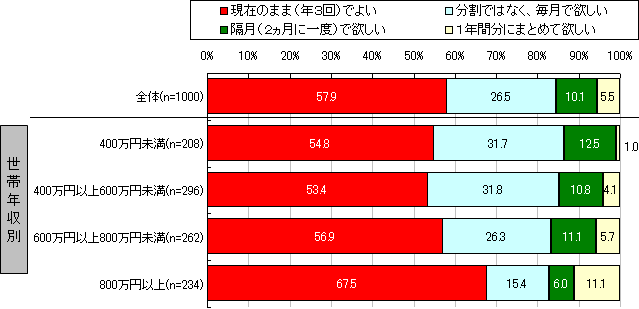
【図6-2】子ども手当の支給方法について(回答理由) ※一部抜粋
<現在のまま(年3回)でよい>
- 気が付いたら振込されている方がうれしい。毎月だと期待してしまいそうだから。(36歳)
- 毎月もらうことになると生活費になってしまいそうなきがする。まとめてもらうと逆に旅行などに使ってしまいそう。年3回なら半分は子供のために貯蓄、半分は足りないもの買うなど計画的に使えそう。(30歳)
- 同じ額もらえるならば、それで満足だから。(27歳)
- 児童手当の分割支給と変わらないので、慣れている。(36歳)
- 貯金にしておるため、特に支給時期については希望はない。(33歳)
- 毎月貰うと、生活費につかってしまいそうなので。(49歳)
<分割ではなく、毎月で欲しい>
- 忘れた頃に支給になるので、結局使い道が見つからず、貯蓄にまわっている感じ。毎月支給されたほうが、教育費などに当てやすい。(34歳)
- 「月13,000円支給」とうたっている制度なので毎月振り込むべきではないかと思うので。(30歳)
- いつ打ち切られるか分からないので、少しずつでも受給しておきたい。(32歳)
- 使い道として学資保険や保育料に充てたいので、毎月のほうが使いやすい。(30歳)
- 毎月の生活費にいっぱいいっぱいで支給月まで生活がもたない。(27歳)
- 年3回は計画が立てにくい(42歳)
<隔月(2カ月に一度)で欲しい>
- たまに大きな収入より比較的頻回にもらえるほうが日々の生活に使いやすい。また、あまり期間が空くと、本当にもらえるのか不安になりそうだから。(35歳)
- 4ケ月に一度ではなく、2ケ月程度に1度の方が支給されている感じがする。忘れた頃に振り込まれるのであまり支給について実感が沸かないので。(30歳)
- 3ヶ月だと入る金額は大きいが2ヶ月間隔のほうが本当に家計が大変な人は月ごとに厳しいと思うので間を取って2ヶ月に1度がいいと思う。(33歳)
- 年3回だと何月に振り込まれるのかを忘れてしまいそうなので、分かりやすい隔月にして欲しいです。(39歳)
<1年間分にまとめて欲しい>
- 全て貯金に回しているので使わないので年1回でいい。(31歳)
- 税金等お金のかかる3-4月にもらえると家計が助かる。役所としても手続きが年に1回の方が手間と手数料がはぶけて良いのでは。(41歳)
- 一度にいただいたほうが使い道を考えやすい。(35歳)
NTTコム リサーチは、平成24年10月1日にエヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社からNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社へ事業譲渡され、平成25年12月9日にgooリサーチより名称変更いたしました。gooリサーチの調査結果(共同調査含む)等についてはこちらまでお問合せください。